国際結婚や海外生活をしていると、子どもの言語環境はとても複雑になり日本語の成長に不安を感じる
時がありますよね。
わが家は私が日本人、妻が韓国人、そして現在はニュージーランドで生活しています。
家庭内に日本語、韓国語、英語の3つの言語が共存する、いわゆる「多言語家庭」です。
移住したばかりの頃の私の職はシェフで、帰宅時間が遅く子どもとの時間も不足がちでした。
妻は日本語が話せるので、私がいない時間にもひらがななどを教えてくれたりと日本語に触れる機会を作ってくれていましたが、やはり子どもは母親と一緒にいる時間が長いので、母親の言語が中心になっていきます。
そしてだんだんと私が日本語で話しかけても、韓国語でかえすことも多くなっていました。
そんな時に訪れたのが、あのコロナによるロックダウンでした。
基本的に外出禁止、エッセンシャルワーカー以外は仕事もできません。
突然訪れた、毎日息子と向き合える膨大な時間。
これはチャンスだと思い当時3歳の息子と日本語に向き合う方法を考え、そして行ったのが「絵本の読み聞かせ」です
毎日絵本を読み語ることで、語彙が少しずつ増えていき私の日本語の問いかけに対して、日本語でかえしてくれるようになっていきました。
小さなきかっけで子どもは日本語を話さなくなったり、また話すようになったりします。
この記事では、私たち家族が経験したきっかけとそして親として大切にした視点を記録として残しながらご紹介します。
海外での継承語育児に取り組む方や、子どもの言語バランスに悩んでいる方の参考になれば幸いです。
家庭内言語の取り決めを守るのは親の責任
わが家の家庭内言語のルールは息子が産まれた時から
・妻(母親)は韓国語で話しかける
・私(父親)は日本語で話しかける
でと決めていました。
息子が言葉を話し始めてからは、息子は母へは韓国語、父へは日本語というルールを追加しました。
しかし、妻も私もお互いの言葉を話せるのでフレーズの中に日本語と韓国語が入り混じっている事も多くあり、特に父親の私はルールをよく破り、親子3人で会話をしている時に韓国語で話してしまう事が多くありました。
そのため息子の頭の中に、お父さんにも韓国語で話しても大丈夫という認識が、小さい時からできてしまっていたようです。
妻からは「あなたが日本語で話さないと日本語ができなくなっちゃうよ」とよく言われていましたが、私が子どもの言語教育にそこまで強い意識を持っていなかったため、強い意志をもって日本語で話すことをしていませんでした。
増えていく韓国語の使用
ニュージーランドは移民が多い国なので、さまざまな国の人が生活しています。
特に私たちが住んでいる最も大きな都市であるオークランドは街を歩いていると、色々な言語が聞こえてきます。
 ろは
ろは家庭内では母親と父親が違う言語を話していたり、外に出ても体格や見た目が全く違う人たちがさまざまな言葉を話していることが当たり前の環境に小さい時からいたことで、色々な人がいるということを肌で感じさせることができ、息子の成長にはよい影響を与えることができたと思います
小さい子どもを数時間、遊ばせることができるプレイグループをおこなっている場所がたくさんあり、様々な人と交流もできます。
またニュージーランドは韓国人の移民の方も多く、海外での子育てということで同じ悩みを抱えている、同じ国同士のママ友との交流がメインになっていきました。
外で会うのは韓国人の友人が多くなってきたので、子どもが韓国語に触れる機会は増えていきましたが、それに伴い日本語に触れる機会は相対的に減っていきました。
言葉を発し始めたころは、夫婦で別々の言語で話しかけても、ちゃんと別々の言語で返答していたり、オウムかえししていた息子が少しずつ私が日本語で話しかけても、韓国語で返答するようになってきました。
振り返ってみれば、決まりを守れなかった私のせいで息子は日本語を失う可能性もありました。
周りの国際カップルをみても、子どもが片方の親の言語しか話せない場合は、ほとんどが母親の言語です。



多言語教育には父親の意思と協力がとても大切です
ロックダウンで生まれたことばの時間
このままではいけないと思ってながらも、休みの日以外はなかなか時間を作れず時間だけがすぎていました。
しかし私がいない時も、日本語も話せる妻はひらがな表を自作して息子にひらがなを教えてくれていたり、日本語の絵本を読んでくれたりと、日本語に触れる機会を作ってくれていました。



韓国語だけにならないように、日本語の教育まで考えて実行してくれていた妻には本当に感謝しています
突然おとずれた最初のロックダウンと子どもとの時間
子どもが2歳になるちょっと前のそんな中、世界中で猛威をふるっていたコロナウイルスのパンデミックが、ついにニュージーランドにも広がり始めました。
そしてその影響は急速に深刻化し、ついにはエッセンシャルワーカー以外は外出禁止の全国的なロックダウンが実施され、私たち家族も毎日家で過ごす生活となりました。
突然訪れた一日中家で過ごす毎日の時間。
「子どもとの言葉の関係を変えるには今がチャンスかもしれない」
私はそう思い、日本語の絵本の読み聞かせを毎日欠かさずおこなうようにしました。
最初の頃によく読み聞かせたのは、「もいもい」や「がたんごとん」のように繰り返し表現が多くリズム感がある作品や、「0歳のえほん」「1歳のえほん」のように、語りかけや童謡などがあって一緒に遊びながら楽しめる作品を選んでいました。
息子が楽しく日本語の絵本に入りこめた理由は、この4冊には2つポイントがあったからだと思います。
リズムで日本語を口にする
語感がただ楽しく感じることができる「もいもい」は日本語を口にするようになる、とてもよいきっかけになった1冊でした。
言葉自体には意味はありませんが、ひらがなを見ながら私の言葉を、大笑いしながら一緒にまねをする、こんな繰り返しが日本語のスイッチを作るきっかけになりました。
「がたんごとん」は子どもが好きな「電車」の音を日本語で口にするきっかけをつくり、また動物やあいさつを覚える入り口になりました。
どちらの作品も、繰り返しのリズムで子どもが楽むことができ、絵本の読み聞かせよいうよりも、一緒にことば遊びをしている感覚で日本語に触れる機会を増やすことができました。
一緒に話しながら楽しむ
「0歳のえほん」と「1歳のえほん」は語りかけや、童謡があって、子どもと一緒に楽しめる作品でした。
この2冊は絵本を読むというより、童謡や体操で一緒に遊んだり、各ページにでてくる「車」や「情景」を使って話を広げて、私の語りかけに息子が答えるというような遊びをしていました。
この繰り返しが、息子の口から日本語で答えるというきっかけを作ってくれたと思います。
また、この絵本の巻末に載っていた、○○か月の子どものできることリストが私にはとても参考になりました。
繰り返しがもたらした変化
そもそもこの時は、まだニュージーランドに来て1年未満で、日本の絵本もそんなにたくさんは持ち合わせていませんでした。
それでも持っている絵本を何度も何度も読み聞かせ、一緒に童謡を歌ったりて初のロックダウンという先の見えない日々を「子どもと毎日過ごせる楽しい日々」と考え、毎日を少しでも楽しくすごしました。
そんな完全なロックダウン生活も1か月ほどつづき、毎日絵本を読み聞かせるのが完全に生活の一部となると、息子の発する言葉にも変化がおこりました。
以前までは犬のことを韓国語でワンちゃんという意味の「멍멍이(モンモンイ)」と言っていたのが、日本語で「わんちゃん」というようになったり、絵本で覚えた擬音語などは日本語で伝えてきたりなど明らかに日本語を口にすることが増えてきました。
もともとわが家は本を読む習慣があり、息子も本を開いて見ることが好きだったので、絵本の読み聞かせを始めても、もっともっとという具合に楽しく行なうことができました。



これもそんな土台を作っていてくれた妻に感謝です
2度目のロックダウンと言葉の習慣化
完全なロックダウンは1か月ほどでおわりましたが、外出制限のある生活はまだまだ続きました。
飲食業はテイクアウトのみの営業が許可され、私はまた仕事が始まり時間は減ってしまいましたが、休みの日などは絵本の読み聞かせを続けていきました。
読み聞かせを続けていると次の段階としてお話がある絵本が欲しくなり、日本から何冊かとりよせたりもしました。
またそんな中、職場の日本人の方に大量の日本の絵本や子どもの本をいただき、わが家には読み切れないほどの本が
やってきました。
息子はたくさんの自分の絵本がうれしかったようで、私が読むの絵本の渋滞ができていました
そんな中、息子が3歳を迎えた8月にデルタ株による2度目の完全ロックダウンが発令され、また子どもと毎日を過ごすことができる日々がやってきました。
今回も絵本を読み聞かせる毎日です。
しかも今回は絵本がたくさんあり、既に息子からの「読んで下さい」渋滞ができている状態です。
毎日毎日、日によっては一日中絵本を読むこともありました。
この時のロックダウンは1か月以上続きましたが、その間にお気に入りの絵本は全文を覚えてしまうほど息子は日本語に触れていました。
私がひとつのフレーズを読み上げると、あとに続いて息子が覚えた文章を話しだすといった具合です。
この時とってもお気に入りだったのが、一冊に短いお話がたくさんでてくる「3さいのおはなし」、キャラクターがとてもかわいい「バムとケロ」シリーズ、「こぐまちゃん」シリーズでした。
特に「3さいのおはなし」は長さがちょうどよく、ほとんどのお話を覚えてしまい、「バムとケロ」では曜日を覚えることができました。
このころには私が日本語で話しかけると、また日本語で反応するようになってきました。
お母さんとは韓国語、お父さんとは日本語というように言葉のスイッチがこの時できたような気がします。
またこの時は、YouTubeで童謡もたくさんききました。
歌のお兄さんが歌ってくれるチャンネルの童謡が気に入ったようで、「大きな栗の木の下で」などを一緒に踊りながら歌って覚えました。
2度目の完全なロックダウン、しかもその間も小さな制限付きのロックダウンを繰り返していたので、私たち家族も最初のときより心に余裕があり、貴重な楽しい家族のことばの時間を過ごすことができました。



ロックダウンがあったから、息子のことばと向き合うことができたので
大変な経験でしたが、わが家にとってロックダウンは非常に意味のある時間でした
言葉は揺りもどされる
ロックダウンのおかげで、息子は日本語を話すようになりました。
とはいえ、気を抜くとまたすぐに韓国語に引っ張られます。
多言語育児において避けられないのが「揺り戻し」です。
ロックダウンが完全におわりニュージーランドにも日常がもどってくると、今までの反動で私の仕事も忙しくなり、また韓国人の友達と会う時間が増えるようにもなりました。
その様な状況になるとと、また韓国語が優勢になっていきました。
私自身も、忙しさに、かまかけて韓国語で受け答えしてしまうことが増え、気づけばまた日本語の使用頻度が減っていく…..そんなサイクルが何度か訪れました。
つまり私が日本語使用を緩めると、子どももすぐに戻ってしまうのです。
これは最初に「お父さん→韓国語が通じる人」
と認識させてしまった私の責任です。
私が意識をもっと強く持つことが大切だったのです。
そしてこのころから「日本語を話してほしい」ではなく、「私が日本語を話し続ける責任がある」という強い気持ちに変わりました。
この気持ちが、ずっと私には不足していたのだと思います。
この記事を書いている息子が7歳になった現在も油断をすると、韓国語が多くなります。
家族3人で話している時などは、お母さんに韓国語で話をしながらそのまま私にも韓国語で続きを話すことはよくあります。
そんな時は、子どの話していることを相づちうつ、タイミングで日本語で言い直して「それでどうなったの?」と日本語で話の続きをうながすようにしています。
そうすることで息子は「あっ!」と気づき、がんばって続きを日本語で話してくれるようになっています。
まだ息子が一番ストレスを感じず話せるのは、韓国語です。
これが将来は英語になっていくかもしれません。
それでも、息子には日本語を自由に使えるように、私が努力していきたいと考えています。
親ができること
多言語育児は、子どもに任せれば自然に…..とはいきません。
強い意志を持ちながら、やさしくてあたたかい言葉環境を作っていくことが大切です。
読み聞かせ、声かけ、子どもの気持ちに寄り添いながら、日々少しずつ日本語の居場所を作り上げていく作業。
それは、親である私自身の言葉への姿勢の確認でもありました。
子どもがどんな言語を使うかは、たくさんの要因でかわります。
わが家はロックダウンという出来事をきっかけに家族のことばの関わり方に大きな変化がありました。
そして、小さなことの積み重ねが確かな変化をもたらすことも知りました。
海外での多言語育児において、日本語が消えてしまいそうだと感じることがあるかもしれません。
環境を作り続けることが、難しいときもあるかもしれません。
そんな時は、なぜ子どもに日本語を話して欲しいのか、伝えていきたいのかを、一度よく考えてみるといいかもしれません。
言葉は生きもの、育てるには時間と関係性が必要です。
だからこそ、あせらず、あきらめず、少しずつ丁寧に。
こんな姿勢で子どもと向き合えばきっと親の気持ちは子どもに伝わると思っています。
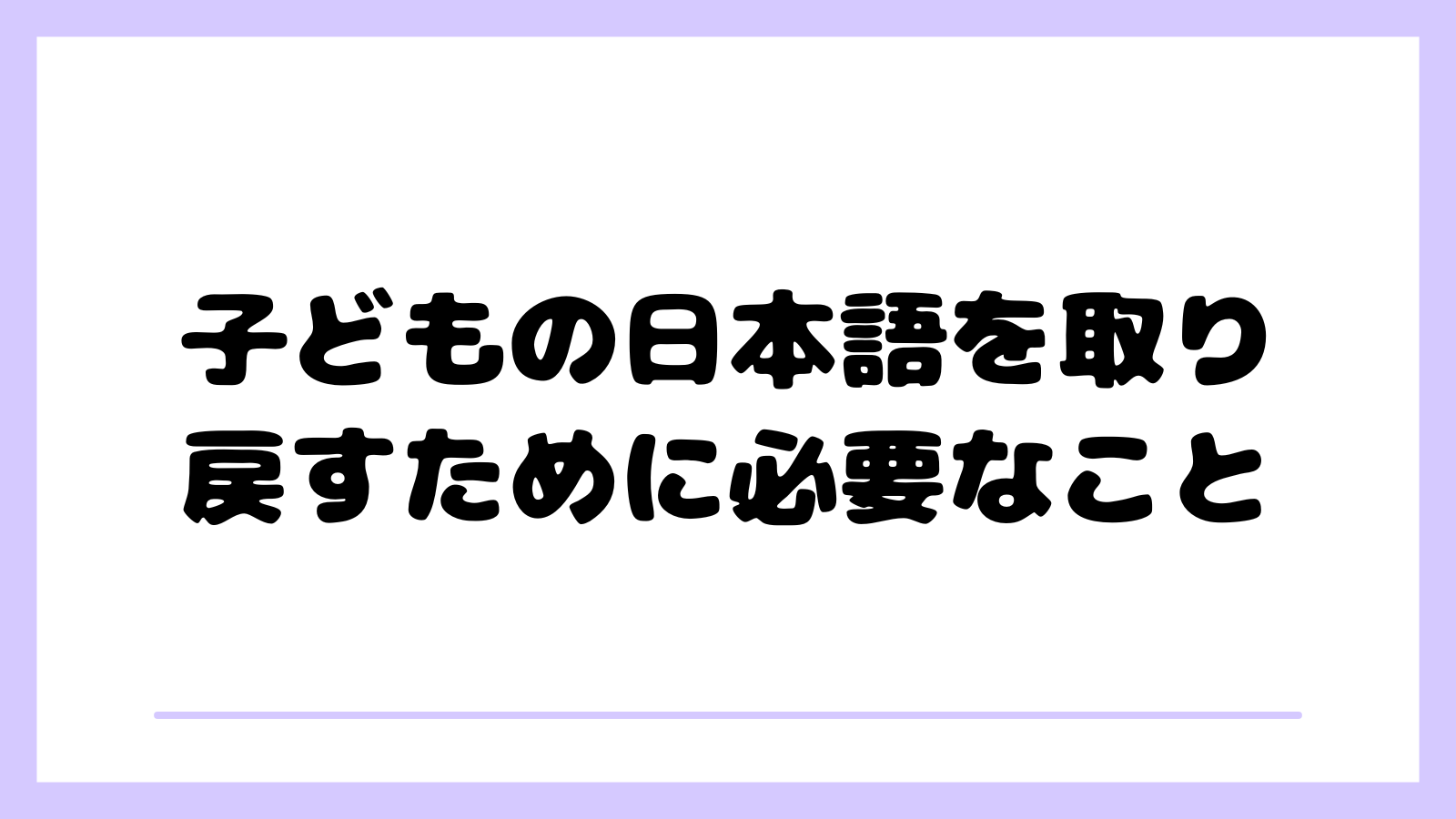




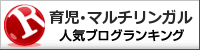
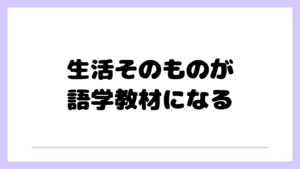
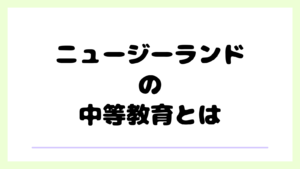
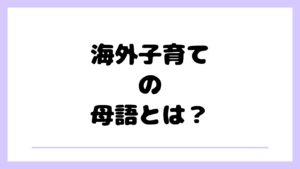
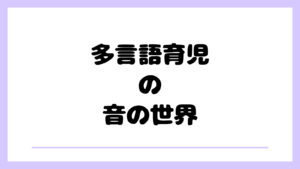
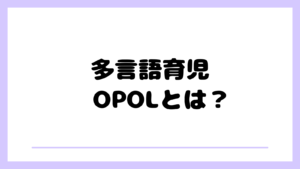
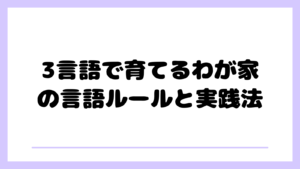
コメント