「ニュージーランドの学校って、どうなってるの?」
移住を考えている人だけでなく、すでにニュージーランドに住んでいる人でも、制度の全体像を把握していない方も多いのではないでしょうか。
ニュージーランドの教育システムは、日本とは異なる点がいくつもあります。
たとえば、「Year0」「Year1」などと呼ばれる学年の始まり、誕生日によって異なる入学時期、4学期制の学年構成、個々のペースで学習が進められるカリキュラム。
そして、移民家庭の子どもたちには「英語サポートクラス(ESOL)」という特別支援も用意されています。
本記事では、ニュージーランドの教育を幼稚園(ECE)から初等教育までのステージを、日本との違いを比較しながら詳しく解説していきます。
それぞれの年齢で何を学び、どのように進学していくのか、親としてどう関わっていくべきかなど、実際に生活する上で知っておきたい情報をまとめました。
全体の流れと義務教育の年齢
ニュージーランドの教育制度の特徴
本題に入る前に、ニュージーランドの教育制度を簡単に説明します。
ニュージーランドの教育制度は以下の3つの段階に分かれています。
・Early Childhood Education(ECE)=就学前教育(0〜5歳)
・Primary and Secondary Schooling(5〜18歳)
・Tertiary Education(高等教育/18歳以降)
義務教育は「6歳から16歳まで」であり、Primary School(小学校)、Intermediate School(中間校)、Secondary School(高校)までがその対象です。
ただし、5歳の誕生日を迎えるとすぐに小学校(Year1)へ入学できる制度になっており、多くの家庭は5歳で入学します。
 ろは
ろはわが家は学校入学前に韓国へ帰国していたので、6歳の誕生日前に入学しました
日本との比較
日本では義務教育が「6歳から15歳まで」となっており、小学校6年間+中学校3年間がその対象です。
高校は義務ではありませんが90%を超えており、大学進学率は60%ほど、専門学校を含めた進学率は80%を超えています。
一方、ニュージーランドでは、高校(Secondary School)は、義務教育として定められているのはYear11(15〜16歳)までで、それ以降のYear12・Year13は進学やキャリア準備のために任意で通う段階になります。
ニュージーランドの義務教育をまとめると以下の通りです。
| 教育段階 | 学年 | 年齢 | 義務教育か |
Primary School | Year 1 – 6 | 5 – 10 歳 | (Year 1 以降) |
Intermediate School | Year 7 – 8 | 11 – 12歳 | |
Secondary School | Year 9- 13 | 13 -18 歳 | (Year 11 まで) (※Year12〜13は任意) |
義務教育を終えると、高等教育に移っていきますが、ニュージーランドの高校では、NCEA(National Certificate of Educational Achievement)という国家資格取得が目標となります。
このNCEA資格認定率を見ると、高校卒業とみなされる、Level 2以上修了者は70%前後、より高い進学(大学・専門教育)や奨学金、職業訓練の条件となる最終レベル(Level 3)取得者は60~70%程度と考えられます。
ニュージーランドでは大学に進学するのは3〜4割程度ですが、ポリテクニックなどの職業訓練機関を含めると、高校卒業者の約7〜8割が何らかの高等教育機関に進んでいます。
日本とニュージーランドでは、「大学進学率」と「高等教育進学率」の意味合いが異なります。
日本では大学と短大・専門学校が明確に区別されますが、ニュージーランドでは大学だけでなく、職業訓練機関(PolytechnicやITPなど)も同じ「高等教育」として扱われます。
そのため、大学進学率よりも高等教育進学率のほうが高くなります。
また、日本が学歴を重視する傾向があるのに対し、ニュージーランドでは将来の職業に直結するスキルや関心のある分野を重視して進路を選ぶ傾向があります。
0〜5歳:就学前教育(Early Childhood Education)
ECE(Early Childhood Education)とは
ニュージーランドのECEは、生後すぐから就学前までの子どもを対象にした教育・保育制度です。
主な種類は以下の通り
- Kindergarten(3〜5歳対象の公的な幼稚園)
- Childcare Centre(0〜5歳対象の保育園)
- Home-based care(ホームベース保育:保育士が自宅で少人数を預かる形式)
- Playcentre(親が主導する協同保育)
各施設の特徴は以下のようになります。
・「キンダーガーテン(Kindergarten)」
3〜5歳が対象で、教育重視のプログラムが特徴です。
資格を持つ先生による指導で、小学校入学準備に最適ですが、保育時間は午前・午後の半日型が一般的です。
・「チャイルドケア・センター(Childcare Centre)」
0歳から預けることができ、最大10時間程度の長時間保育に対応しています。
共働き家庭に人気がありますが、費用はやや高めです。
・「ホームベース保育(Home-based Care)」
保育者の自宅で少人数の子どもを預かる形で、より家庭的な雰囲気の中で柔軟に保育が行われます。
保育者に資格がない場合もありますが、監督者が定期的に訪問します。
・「プレイセンター(Playcentre)」
親が主体となって共同運営するスタイルで、0〜6歳の子どもと一緒に親も参加する保育施設です。
費用は非常に安く、親の学びの場としても機能しています。
各施設を簡単にまとめると以下のようになります。
| 施設名 | 対象年齢 | 運営主体 | 教育重視 | 保育時間 | 費用 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kindergarten | 3〜5歳 | 公的・非営利 | 高い | 短時間(半日) | 安め | 小学校準備に◎ |
| Childcare Centre | 0〜5歳 | 公私混在 | 中〜高 | 長時間可 | 高め | 共働き向け |
| Home-based Care | 0〜5歳 | 自宅+監督機関 | 中程度 | 柔軟(個別) | 中程度 | 家庭的+少人数 |
| Playcentre | 0〜6歳 | 保護者協同 | 親次第 | 親の関与次第 | 非常に安い | 親が主役 |
それぞれの施設に特徴があり、家庭の方針やニーズに応じて柔軟に選ぶことができるのがニュージーランドの幼児教育の大きな魅力です。
また、ECEは政府が「週20時間まで無料」を提供している点が特徴です。
これは3歳から5歳の子ども全員が対象で、認可施設を利用すれば公的補助を受けられます。
一方、ECEは必須ではなく、家庭保育でも問題ありません。
「20時間無償制度」の実情
この制度、「無償」という言葉のために、すごいなという印象を受けがちなのですが、実際には週20時間のみの利用は現実的ではないため、追加料金(optional charge)が発生します。



週5日利用しよう思うと、1日あたり4時間しか利用できないので、残りは追加料金が発生します
制度の「無料」は週20時間までというベース部分であり、それを超える部分に関しては施設ごとにルール・料金が異なり、家庭の実情に応じて費用負担が大きくなるのが現実です。
また、都市部や人気の施設になると、子どもが3歳になる前から事前予約や待機が必要になってきます。
このような点を考えると、費用の面では日本と大きな違いはないのかなと思います。
日本とニュージーランドの幼児教育の「考え方」の違い
1. 教育観の出発点が異なる
日本の幼児教育では、比較的「小学校に向けた準備」「しつけや集団行動」「読み書き・数」など、形式的な学習準備を重視する傾向があります。
一方、ニュージーランドの幼児教育では、遊び中心の学び(play-based learning)がベースで、「子どもが何をしたいか」「どう感じているか」を尊重し、自発性と好奇心を育てる教育方針が徹底されています。
2. ニュージーランドでは「子どもが学びの主体」
ニュージーランドの幼児教育は、「テ・ファリキ(Te Whāriki)」という全国共通のカリキュラムに基づいています。
これはマオリ語で「織物」という意味で、子ども一人ひとりの成長を一枚の織物のように描くことを理念としています。
このカリキュラムは、子どもを「受け身の存在」ではなく、「自ら学びを築いていく存在」として捉えます。
例:
・子どもが葉っぱに夢中になっていれば、それをきっかけに「自然」「数」「色」などさまざまな概念に広げていく。
・教師は「教える人」ではなく、「一緒に探求する伴走者」として接します。
3. 年齢で一律に評価されない
日本では「◯歳だからこれができるべき」「遅れている・進んでいる」という年齢基準の発達評価が多く見られます。
ニュージーランドでは「子どもはそれぞれのペースで育つ」という前提があり、年齢よりも子ども自身の関心や発達段階に合わせたアプローチが行われます。
4. 評価は「結果」ではなく「過程」に注目
日本では「ひらがなが書けるようになった」「お片づけができるようになった」など、できたことに焦点が当たりがちですが、ニュージーランドでは「どうやってできるようになったのか」「どんな試行錯誤をしたのか」など、学びのプロセスが記録され、共有されます。
保育記録も「ポートフォリオ」として残され、家庭と共有されるなど、成長を“物語”として捉える文化が根付いています。
わが子の就学前教育を終えて思うこと
この国の幼児教育にはたくさんの魅力があります。
しかし、同時に「これは本当にこのままでいいのかな?」と感じることも少なくありませんでした。
わが家は、引越ししたことが理由で、「KIndergarten」と「Childcare Center」の二か所に子どもを通わせました。
2つの施設を実際に体験した保護者として感じた、ニュージーランドの幼児教育の素晴らしいと思ったことと、気になったことに以下のことがありました。
自由と遊びを重視する素晴らしさ
まず第一に、ニュージーランドの幼児教育は「子どもの自主性」や「遊び」を中心に据えており、その点は本当に素晴らしいと感じました。
・毎日が遊び中心で、子どもが“やりたいこと”を軸に生活できる環境が整っています。
・カリキュラムというより「探究型」のアプローチが多く、自分の好きな遊びや活動を通して、内発的な学びや発見を大切にする姿勢が感じられました。
・指示待ちではなく、自分で考えて行動する力を育てようとしている点も、長い目で見ればとても大切な土台だと思います。
息子も実際に、毎日楽しそうに園に通い、その日やったことを笑顔で報告してくれる日々でした。
「子どもが自分らしくいられる」ことを第一に考えるニュージーランドの教育は、型にはめることなく、その子らしい成長をサポートしてくれる柔軟性にあふれています。
自由がゆえの“気づきにくさ”と“リスク”
一方で、実際に親として子どもを預ける中で、「これはどうなんだろう…」と感じる瞬間もありました。
自由と個性の尊重を掲げる裏には、いくつかの見落とされがちな課題も潜んでいます。
1. 消極的な子が取り残されがち
園では子どもの自主性が大切にされるため、「自分から助けを求める」「やりたいことを選ぶ」ことが前提になります。
しかし、息子のように少し控えめで、自分の意思をなかなか外に出せないタイプの子にとっては、この環境が必ずしも居心地の良いものになるとは限りません。
先生たちはもちろん見守ってはいますが、「気づいたら一人でポツンとしていた」「本当は○○がやりたかったのに言えなかった」ということもありました。
“自分で言わないと助けてもらえない”空気感が、時には子どもを孤立させてしまう可能性もあると感じました。
2. 安全面に対する不安
もうひとつ心配だったのが安全面です。ニュージーランドの園では、子どもの自由な探究心を妨げないように、環境もとてもオープンです。
例えば…
釘が落ちていたり、トンカチやのこぎりなど実際の工具が使えるようになっていたり。
敷地内の遊具の構造も、必ずしも“安全第一”で設計されているとは言いがたい場面も。
もちろん、本物に触れる体験の大切さは理解していますが、それでも「これって本当に大丈夫なのかな?」と不安になる瞬間が何度かありました。
全ての園がそうであるわけではないと思いますし、ニュージーランドの幼児教育が「遊びの中で学ぶ」ことを重視し、「個の発達」に光を当ててくれる教育であることは確かです。
けれど、その自由が子どもたちを見えにくい孤立や不安、リスクにさらしていることもあるのではないか、と感じることがあり、自由が時に放任になってしまう時があるのではと感じました。
また、英語がほとんど分からない状態で入園した息子の場合は特に、自己主張することがむずかしく、時には無視をされているのではないかと感じることもありました。
最初に通ったKIndergartenでは、園から届くその日の活動や、成長の記録の写真に息子が映っていることがとても少なく、引越しで園を移動する時に渡された息子の成長の記録のポートフォリオには、ほとんど息子の写真がなく悔しい思いもしました。(これはおそらく、息子の担当だった先生の問題だと思いますが・・・)
その後、引っ越し後に通ったChildcare Centerは、よりアットホームなところで、色々ケアもしてくれましたが、私たちも最初の経験から、色々と園に言葉かけをするように心がけました。
日本ではないので、時には「言いすぎかな」と思うくらいに自己主張をしなければ、自分たちにとって不利益になることがあるということを学びました。



息子にはつらい経験をさせてしまったかもしれないと、いまだに後悔することもあります
5〜12歳:Primary School(プライマリースクール/初等教育)
ニュージーランドの小学校制度
ニュージーランドの小学校は、Year1(5歳)からYear6(10〜11歳)までの6年間を指します。
| 学年 | 年齢(目安) |
|---|---|
| Year 1 | 5〜6歳 |
| Year 2 | 6〜7歳 |
| Year 3 | 7〜8歳 |
| Year 4 | 8〜9歳 |
| Year 5 | 9〜10歳 |
| Year 6 | 10〜11歳 |
学期(Term)のサイクル
ニュージーランドのプライマリースクールの年度は、4つの学期(Term)と3回の短いスクールホリデー、そして1回の長いサマースクールホリデーで構成されています。
年度全体は、通常2月初旬から始まり、12月中旬に終了します。
Term 1:
年度は2月初旬に始まり、4月中旬のイースター休暇頃まで続きます。新しい学年のスタートであり、学業の基盤を築く期間です。
4月のスクールホリデー:
Term 1とTerm 2の間には、通常2週間の短い休暇があります。
Term 2:
4月下旬から始まり、7月初旬まで続きます。この学期には、国王誕生日(King’s Birthday)の祝日が含まれます。
多くの場合、ニュージーランドでは冬の到来を感じ始める時期にあたります。
7月のスクールホリデー:
Term 2とTerm 3の間には、再び2週間の休暇があります。
これは冬のホリデーとして知られています。
Term 3:
7月下旬に始まり、9月下旬まで続きます。
この学期は、春の訪れとともに、学業が本格化する時期です。
9月/10月のスクールホリデー:
Term 3とTerm 4の間にも、2週間の休暇があります。
一般的に「春休み」と呼ばれます。
Term 4:
10月中旬に始まり、12月中旬まで続きます。この学期は年度の最終学期として、様々な学校行事やイベントが行われます。
サマースクールホリデー:
年度の最後には、12月中旬から翌年の2月初旬まで、約6〜8週間にわたる長期の休暇があります。
これはサマースクールホリデーと呼ばれ、家族が旅行やレジャーを楽しむのに最適な時期です。
この長い休暇を終えて、新年度が始まります。
このように、ニュージーランドのプライマリースクールは、約10週間の学期と2〜3週間の休暇が交互に訪れるサイクルで運営されています。



実際子どもを通わせ始めると、えっもうスクールホリデー?!というように休みが多いイメージです
入学時期
子どもは5歳の誕生日に最も近い月曜日から小学校に入学できます。
この制度は「ロールリング・エントリー(rolling entry)」と呼ばれ、日本のように4月に一斉入学ではありません。
しかし、現在ははこの「ロールリング・エントリー」だけではなく、子どもの誕生日を起点に、学期ごとに定められたグループ入学日(コホート・エントリー)に入学する方式をとる学校も多くなっています。
また、基本的にコホート・エントリーを採用しながら、ローリング・エントリーも受け入れる学校も多いようです。



息子の通う学校は、学校情報ではコホート・エントリ―は’NO’になっていましたが、学校からは特に希望がなければ新学期に合わせて入学してくださいとの連絡がありました
Cohort Entry(コホート・エントリー)とは
・子どもたちを同じタイミング(各学期2回、年に最大8回)でまとめて入学させる制度です。
・ニュージーランドでは長らく、子どもが5歳の誕生日を迎えたらすぐに入学できる「随時入学(Rolling Entry)」が主流でしたが、2018年から政府の方針により「Cohort Entry」が導入可能となりました。
この制度では、新入生が5歳の誕生日を迎えたのち、各学期に学校が定めた最大2日間の特定の日に、まとめて入学する制度です。
そして、このCohort Entry(コホート・エントリー)は個々の子どもの誕生日ごとに入学させるのではなく、グループで入学させることで、先生やクラスの子どもたちが新入生を歓迎し、よりスムーズに学校生活に慣れることを目的としています。
これにより学級運営が安定し、教師も一貫した指導がしやすくなるというメリットがあります。
Cohort Entry(コホート・エントリー)をまとめると以下のとおりです。
目的:
個々の子どもの誕生日ごとに入学させるのではなく、グループで入学させることで、生徒たちがよりスムーズに学校生活に慣れることを促し、安定した学級運営と指導を目的。
最大日数:
1つの学期(term)につき、最大で2日間の入学日を設けることができ、1年間(4学期)を通して、最大8日間。
学校の裁量:
・コホート・エントリー制度を導入するかどうかは、各学校が自由に決めることができる。
・導入する場合でも、最大8日すべてを使う必要はなく、学校の判断で日数を減らすことができる(例:各学期の初日のみ、年間4日など)。
・入学日の設定は、学校が保護者や地域社会と協議して決定する。
代替策:
コホート・エントリーを導入していない学校では、従来通り、子どもが5歳の誕生日を迎えたら、その日からいつでも入学できる。
簡単に言えば、コホート・エントリーは、「5歳になったら、いつでも入学できる」という選択肢に加えて、「みんなと一緒に、決まった日から入学する」という柔軟な選択肢を学校が提供できるようにする制度です。
また多くの場合、子どもと家族を歓迎するための儀式や集まりが入学の日や別の決められた日に行われます。
日本の入学式とはちょっと違いますが、ニュージーランドの学校におけるコホート・エントリーでは、多くの場合、マオリの儀式である、Mihi Whakatau(ミーヒ・ファカタウ)が歓迎の儀式として採用されます。
これにより、子どもたちや家族は、マオリの文化に触れながら、温かく迎えられることができます。
息子のかよう学校は、入学後に学校から、「来週は新入生を歓迎する儀式がありますよ」という旨のメールがあった程度だったので、生徒の行事のひとつだと思い、私たち両親は見に行きませんでした。
学校にもよると思いますが、息子が通う学校は、親が皆かけつけておこなわれるような式ではなかったようです。
学びの特徴
ニュージーランドの小学校は、単に知識を詰め込む場所ではありません。
子どもたちが安心して失敗し、挑戦し、自分らしい輝きを見つけられる場所が小学校です。
そんな温かいコミュニティの中で、子どもたちは生き生きと学びを深めていくのです。
「遊び」から始まる、探究心あふれる学び
ニュージーランドのプライマリースクールの低学年では、机に向かって座って勉強する時間ばかりではありません。
むしろ、机に向かっている時間はほとんどないと言っても過言ではないかと思います。
「遊び」こそが、彼らにとっての重要な学習の場になります。
レゴブロックで複雑な構造物を作ったり、水遊びで重力や浮力を学んだり、泥だらけになりながら自然を観察したり。
子どもたちは、好奇心のおもむくままに遊び、そこから科学や数学、社会の仕組みを自然に学んでいきます。
先生は、この遊びの中に隠された「学びの種」を見つけ、それを深める手助けをします。
これは「探究学習(Inquiry-based learning)」と呼ばれるもので、「なぜ?」「どうして?」という子どもの素朴な疑問を大切にし、自ら答えを探し出す力を育むことを重視しています。
学力だけでなく「生きる力」をはぐくむ教育
ニュージーランドの教育は、読み書きや計算といった学力だけでなく、子どもの心と体の全体的な成長を重視します。
「回復力(resilience)」や「自主性(independence)」といった社会性を育むことが、カリキュラムの重要な柱です。
例えば、子どもが自分で問題を解決しようと試みる姿勢を尊重したり、失敗を恐れずに挑戦する気持ちを称賛したりします。
また、運動やアート、音楽といった教科を通じて、自己表現の楽しさを学び、協調性を育みます。
多様性を尊重する温かいコミュニティ
ニュージーランドは多文化社会であり、学校もその多様性を大切にしています。
息子のクラスも、マオリを含むニュージーランド人はもちろん、アジア系、ヨーロッパ系、アイランダーと呼ばれるポリネシア系と様々な子どもが集まっています。
また、先住民族マオリの文化は、教育のあらゆる側面に深く根ざしています。
マオリの儀式があらゆる場面でおこなわれたり、学校を「kura(クラ)」や生徒を「ākonga(アコンガ)」と呼んだりと、あらゆるところでマオリ語が使われたりいます。
Year0ってどういうこと?
ニュージーランドの小学校は、Year1(5歳)からYear6(10〜11歳)までの6年間と聞いていたのに、実際に小学校の準備や情報を集めているとyear0という存在をしりました。
このyear0とはどういうことなのでしょうか。
・「Year 0」とは、主に7月から12月の間に5歳になり、その年度中に小学校に入学する子どもたちに対して使われる非公式な呼称です。
・7月以降に入学した生徒は、その年度の残り期間をYear 0として過ごし、翌年の2月(新年度のTerm 1)に正式にYear 1に進級します。
これは、教育省が生徒数を基に、学校への資金や教員数を予測・決定するための生徒登録報告が、7月1日の生徒の在籍数に基づいて行われるため、7月以降に入学する子どもたちがその年度の資金計算には含まれないことが大きな要因のひとつになっています。
つまり、7月1日以降に5歳の誕生日を迎える子ども、および6月生まれで7月1日時点ではまだ入学手続きが済んでいない子どもは、7月1日の生徒数カウントに含まれないため、その年度の資金計算の対象外となります。
そして、7月1日以降に入学した子どもたちは、翌年度の資金計算には含まれるものの、その年度の残り期間は追加の資金提供が限定されるため、Year 0として、翌年のYear 1進級を前提としたクラス編成が行われます。
また、6月生まれの子どもは、「ロールリング・エントリー」で入学すると、資金計算には含まれますが、「Yearレベルの分類ルール」が別に適用され、、同様に「Year 0」として年度の残りを過ごします。



ちょっとわかりずらいですが、1月から5月生まれと6月から12月生まれで分けられるということです。
また、12月中旬にはterm4が終わり、長いサマースクールホリデーに入ります。
その為、12月生まれでも、誕生日がスクールホリデー以降の子どもは、year0に入学することなく、翌年の新学期にyear1から入学することになります。
まとめると、
・1月~5月生まれ → Year1 入学
・6月~12月生まれ → Year0 入学
・12月生まれでもterm4が終わっていれば、翌年のterm1からYear1 入学
表でまとめると以下のようになります。
| 学年 | 年齢 |
| Year0 | 5歳 |
| Year1 | 5~6歳 |
| Year2 | 6~7歳 |
| Year3 | 7~8歳 |
| Year4 | 8~9歳 |
| Year5 | 9~10歳 |
| Year6 | 10~11歳 |
英語サポートクラス(ESOL)とは?
ESOLとは、「英語を母語としない子どもたちが、学校での学びに必要な英語力を身につけるための無料サポートプログラム」です。
ニュージーランドでは、移民や留学生など、多様な言語背景を持つ子どもたちが多く在籍しており、わが家の息子のように英語にまだ慣れていない子どもも多くいます。
ESOLは、そうした子どもたちが学校生活や授業にスムーズに適応できるように、読み書き、聞く話す、語彙、文法など、基礎から丁寧に英語を教える特別なクラスやサポートです。
対象者は英語を第一言語としない、プライマリースクールから高校にあたるYear 13までの生徒がふくまれます。
特徴としては、
・少人数グループまたは個別指導で行われることが多く、子どものレベルに合わせた指導が受けられます。
・通常の授業時間の一部を使って行われるため、教室での授業と並行して学びます。
・英語だけでなく、算数や理科の英語用語、授業で必要な表現なども学ぶことがあります。
・ESOLの先生は、英語が第二言語である子どもたちの指導に特化したスキルを持っています。
学校の先生が「英語での理解が難しい」と判断した場合に、ESOL対象となることもあり、ESOLプログラムは、新しい環境で学ぶ子どもたちが、言語の壁を乗り越え、自信を持って学校生活を送るための重要な役割を担っています。
わが子がプライマリースクールに通い始めて思うこと
わが家では、息子の手術の関係で5歳の時に母親と長く韓国に帰国していた為、6歳のterm1から入学しました。
4月生まれの為、本来は5歳からYear1入学だったのですが、英語も得意ではなかったので、義務教育開始の前に帰国をして、6歳からの入学を選択しました。
このように、家庭の都合や、考え方で入学時期を選べるのはよい点だと思いました。
社会自体が年齢を気にするような空気はないので、5歳でYear1 でも6歳でYear1でも気になることはありません。
日本の学校のように、45分間を机に向かって座って授業を受けるということもなく、非常にのびのびとしていて自由な半面、集中力などが同じ年齢の日本の子どもに比べて足りなかなと思うこともあります。
なにより、私が見る限りでは、学校ではほとんど遊んでいるようにしか見えません。
本人は否定していますが(笑)。
先輩の移民の方からは、学年が上がるにつれて学力の心配事などがでてくると聞いていますが、低学年である、今のところはとてもいい環境ではないかなと思っています。
まとめ
ニュージーランドの教育システムは日本と違うことが多いので、複雑でわかりずらいことも多いです。
また幼稚園の20時間無料や、5歳の誕生日順に入学など、言葉からの情報でもっていた印象と、実情のシステムとはちょっと違うことがあります。
それでも、色々なことが一律で決まっているのではなく、わが子にあった選択ができることはとてもよいシステムだと思います。
また、小学校では思っていたよりも、スポーツなどの課外活動が充実しており、希望すれば色々なことに挑戦させてあげることもできます。
なにより、子どもがのびのびとしている姿を見ると、子どもにとってはとてもよい環境なのかなと感じます。
一方で、学力については少し不安も残ります。
その為、家庭でのフォローも大切になってくることでしょう。
ただそれも含めて、全てを学校に任せるのではなく、家族全員で関わっていくのがニュージーランの学校生活なのかなと思います。
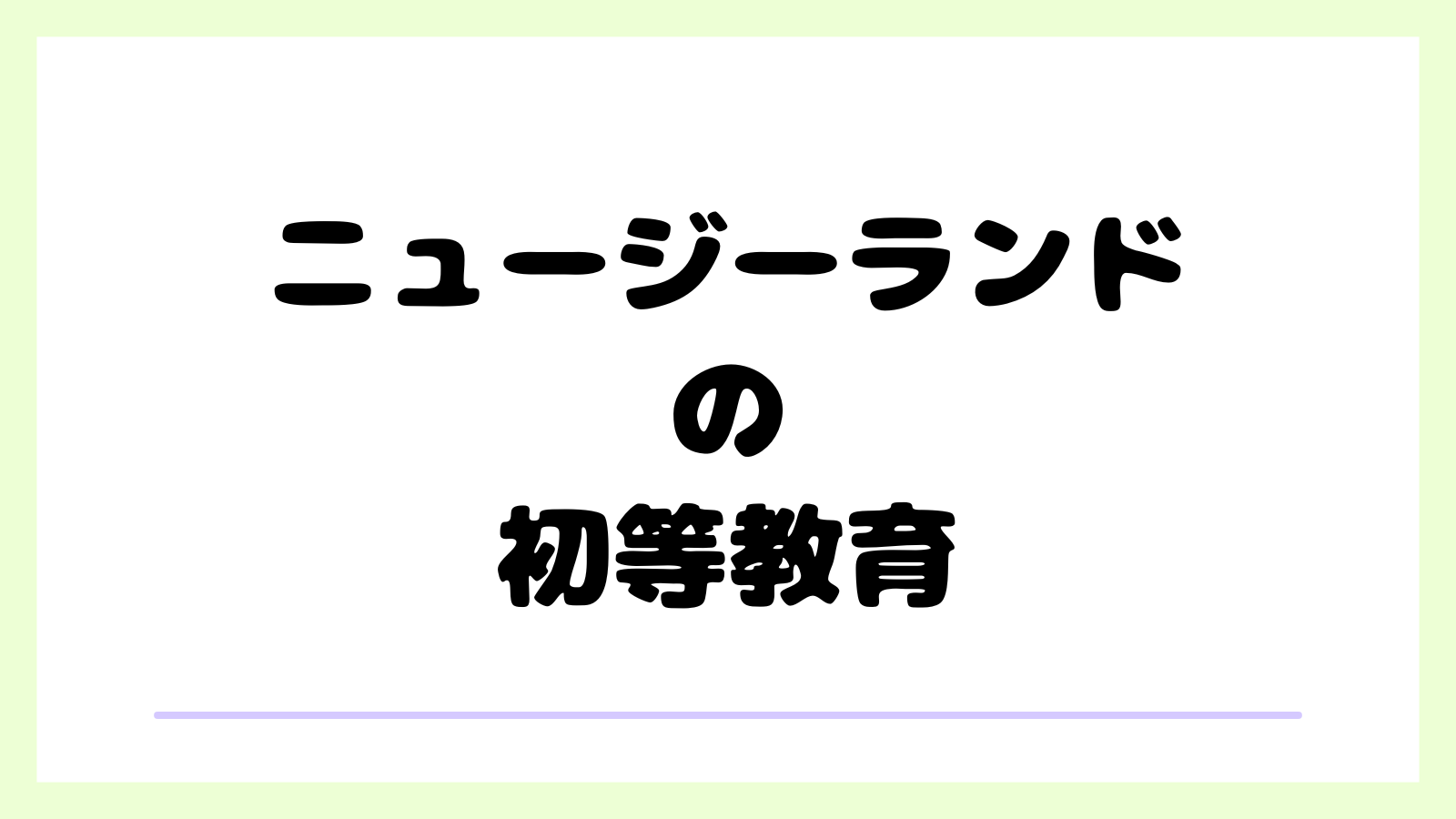

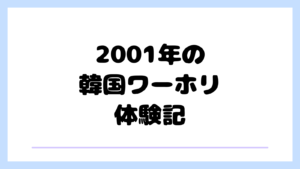
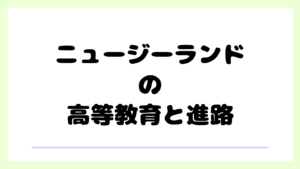
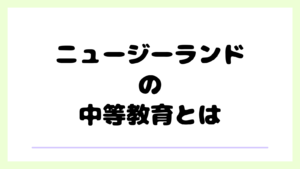
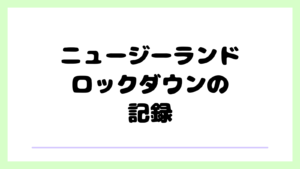
コメント