子どもと暮らしていると、「そんな言い方、どこで覚えたの?」と驚かされる瞬間がよくあります。
単語ひとつ、言い回しひとつが、大人の予想を超えたタイミングで飛び出してきて、思わず笑ってしまったり、感心したり。
これは多くの家庭で経験することですが、多言語家庭ではその頻度がさらに高くなります。
わが家は、私が日本人で妻が韓国人。
7歳になる息子と、ニュージーランドで暮らしています。
家のなかでは私と息子は日本語で会話し、妻と息子は韓国語でやりとりし、家族全員で話すときには自然に両方の言語が入り混じります。
そして一歩外に出れば、学校や友達とのやりとりはすべて英語。
つまり息子は、日常のなかで三つのことばの世界を行き来しているのです。
この環境に特別な教材や意識的な訓練があるわけではありません。
あくまで生活そのものが「三言語の舞台」になっているだけ。
しかし子どもにとっては、それが最高の学びの場になっているようです。
耳に入ったフレーズを心のどこかにしまい込み、必要なときや「ここだ」と感じたときに、まるで宝箱から取り出すように言葉を口にします。
大人からすると「そんな難しい言葉を、どこで?」と思うような表現も、本人にとっては日常の一部。
繰り返し耳にした音が、生活の場面と結びついて自然に飛び出すのです。
この記事では、そんな日々のなかで起きた、子どものことば拾いのエピソードをご紹介します。
特に、子どもの他言語教育で悩んでいる方へ、この記事がヒントや助けになれば幸いです。
ニュージーランドで暮らすわが家の「ことば拾い」
私たち家族はニュージーランドで暮らしています。
実際に住んでいる場所は、オークランドというニュージーランド最大の都市ですので、普段の生活の風景は、日本の地方都市に住んでいるような感じです。
しかし、20分程度車を走らせれば、大自然に囲まれたのびやかな環境が広がっているので、、休みの日は家族で郊外に車で出かけることが多くあります。
また、7歳になる息子は車の中で、テレビやスマホを見ることよりも、外の風景を見ていることが好きで、興味のあるものが目につくと後部座席から、日本語や韓国語でいつも質問が飛んできます。
空は高く、丘はどこまでも緩やかに続き、羊や牛が道路わきにも現れながらも、街が突然現れたりもする、そんな景色が多く点在するニュージーランドの郊外のドライブのなかで、今回の“ことばの事件”は起きました。
その日、道の脇に線路と倉庫のような建物が見えました。
線路には、使われなくなって久しいと思われる機関車が、静かに止まっています。
後部座席で窓の外を眺めていた息子が、落ち着いた声でたずねます。
 息子くん
息子くん「あの電車は、なぁに?」
好奇心はあるけれど、はしゃいではいない、いつもの調子。
妻が振り返って韓国語で説明しました。
「저건 옛날 기차야. 증기로 움직였어.(あれは昔の汽車よ。蒸気で動いたんだよ)」と。
そして、蒸気の説明と動く仕組みを簡単な説明を加えて話していました。
すると息子は少し考えてから、さらりと口にしたのです。



「증기배출로 움직이는 거야?/ ジュンギペチュルロ ウンジギヌンゴヤ?」(蒸気排出で動くの?)。
助手席の妻は思わず吹き出し、「いま、なんて言ったの?」と笑いながら確認。
7歳が日常会話で使うには、やけに専門的な言い回しに聞こえます。
私は思わずにやり――すぐに心当たりがあったのです。
炊飯器が語学の先生だった
息子の「증기배출/ ジュンギペチュル(蒸気排出)」は、わが家の台所から来ています。
韓国製の炊飯器は、炊飯や保温の状態を音声で案内してくれるのですが、その中にほぼ毎回登場するフレーズがあるのです。
「증기배출이 시작합니다./ジュンギペチュルリ シジャカムニダ.(蒸気排出が始まります。)」
圧力式の韓国の炊飯器は炊き上がり前に、フタの弁から白い蒸気がシューッと上がります。
その前に、注意喚起のために上記のアナウンスが機械の落ち着いた声で台所に響きます。
大人の私たちには、もはや生活音の一部。
ところが息子にとっては違いました。
いつも同じタイミングで、同じ出来事(熱い蒸気)とセットで流れるフレーズ。
意味は完全に理解していなくても、「蒸気が出る=증기배출/ ジュンギペチュル」という対応関係だけは、繰り返しの体験でしっかり頭に刻まれていきます。
この「同じ場面で、同じ音が繰り返される」という条件は、子どもにとって強い学習信号になります。
単語単体としてではなく、匂い・音・手触り・視覚的な動きといった感覚とセットで入ってくるため、記憶の結び付きが太くなります。
蒸気機関車の説明を聞いたとき、彼の頭のなかで検索が走り、最も鮮明に結びついているフレーズ――「증기배출/ジュンギペチュル」が自動的に選ばれたのだと思います。
つまり彼は、「증기배출/蒸気排出」という言葉を生活のBGMのように自然に覚えていたのです。
それを、たまたま目の前の蒸気機関車と結びつけて口にした。
ただそれだけのことなのですが、親にとってはあまりにも意外で面白い瞬間でした。
私は笑いながら妻に「炊飯器だよ」と答えました。
すると妻も「ああ、なるほど!」と納得しつつ、改めて大笑い。
「毎日聞いてたあのアナウンスか!」と、ふたりで頷き合いました。
子どもの耳の良さ、そして言葉の記憶力には改めて驚かされます。
生活の音が学びに変わるしくみ
ここで少しだけ学び寄りの話を。
多言語環境で育つ子どもは、ことばを“音”として捉える段階が長めに続くことがあります。
文字より先に耳で拾い、場面とセットで覚え、必要なときにそのまま口に出す。
大人の文法感覚から見ると「用語が専門的すぎる」「言い回しが硬い」と感じることもありますが、子ども側のロジックはシンプルです。
①よく聞く
②意味がだいたいわかる
③状況に合っている
この三つが揃えば、言ってみる価値がある。
今回の「증기배출」はまさにその条件を満たしていました。
もうひとつ重要なのは、同じ概念に複数の言語ラベルが貼られることです。
わが家だと「蒸気」は日本語の“蒸気”、韓国語の“증기/ジュンギ”、英語だと“steam”。
さらに炊飯器のアナウンスは“증기배출/ジュンギペチュル”。
どれも“熱い湯気が出ている”という同じ現象を指しますが、使われる場面とセットで記憶されるため、ラベルごとの色味が少しずつ違う。
だから息子は、妻の「蒸気で動くんだよ」という説明を聞いた瞬間、“蒸気”という概念に最も鮮明な音で紐付いている“증기배출/ジュンギペチュル”を取り出したのだと思います。
これは混乱ではなく、複数の引き出しを使い分ける戦略に近い状態です。
本人は戦略と意識していませんが、実際にはかなり高度な対応づけをしていることが多いのです。
生活の音は、語彙の“種”になります。
頻度が高く、場面がはっきりしているフレーズは、覚えやすく、思い出しやすいのです。
さらに多言語家庭では、同じ場面に複数言語のラベルが重なるため、子どもはその都度“どのラベルを貼るか”を選ぶ練習を自然としていることになります。
結果として、コードスイッチ(言語の切り替え)も、彼らにとっては“遊び”に近い感覚で起こります。
多言語家庭で親ができること(実践メモ)
では親は何をすればいいのか。
大げさなことは要りません。
今回のような場面で私たちがやってみて、良かったと感じたシンプルなポイントを三つにまとめます。
第一に、出どころを一緒に探す。
子どもが意外な言葉を口にしたら、「どこで聞いたっけ?」と軽く会話をしてみる。
正解探しというより、本人の記憶を一緒に辿る小さなゲームです。
「炊飯器のやつだ!」と自分で気づけると、子どもは得意顔になり、言葉と体験の結びつきがさらに強くなります。
第二に、場面の意味をそっと足す。
たとえば「증기배출」は“熱い蒸気が出るから気をつけてね”という安全の文脈にある言葉。
そこを短く補っておくと、語彙が“使える知識”に変わります。
「蒸気で動く」と「蒸気を排出する」は近いけれど違う、という違いも、押し付けずにさらっと共有しておくと、次の発話に生きます。
第三に、言語を選び直すチャンスを用意する。
たとえばその日の夜、「蒸気機関車って英語だとsteam trainって言うんだよ」と教えつつ、「韓国語だと증기기간차、日本語だと蒸気機関車って言い方もあるよね」と、別ラベルを見せる。
正誤ではなく、引き出しを増やす感覚です。
実は、親がやらないほうがいいこともあります。
ひとつは、過剰な矯正。
面白い言い回しをすぐに「それは違う」と正すと、試行の意欲が落ちてしまいます。
もうひとつは、説明のしすぎ。
背景知識を長々と語るより、子どもが次に使ってみたくなる“短いヒント”を置くほうが、再現性が高いです。
今回でいえば、「汽車は蒸気でピストンが動くんだよ。蒸気をためて、排出もしながら走るんだよ」くらいの一言で十分でした。
後日、息子がレゴで電車を組み立てながら、「ここが蒸気がでるところね」と私には日本語で、妻には韓国で説明していたのを聞いて、ああ、ヒントは届いたなと感じたのを覚えています。
最後に、ニュージーランドで暮らす視点も少し。
英語が外のメイン言語である環境は、親の想像以上に子どもの耳を鍛えます。
学校や地域のイベントで自然に英語が入り、家の中では日本語と韓国語が交互に出てくる。
その切り替えは最初こそぎこちなく見えますが、毎日の“生活音教材”が橋渡しをしてくれることで、子どもの中に「状況に合わせて言語を選ぶ」という感覚が育っていくように思います。
今回の「증기배출/ジュンギペチュル」も、キッチンの音から線路の上の鉄の塊まで、一本の線でつながっていました。
おわりに:キッチンから線路へ、そしてまた日常へ
「증기배출(ジュンギペチュル)で動くの?」――あの一言は、単なる笑い話にとどまりませんでした。
生活のなかで繰り返し聞くフレーズが、概念と結びつき、別の場面で再利用される。
多言語家庭の毎日は、その連鎖の連続です。だから私たち親にできるのは、特別な教材やレッスンを用意することよりも、日常の中の“ことばの芽”に気づいて一緒に面白がることなのだと思います。
炊飯器のアナウンスという何でもない音が、ニュージーランドの片隅で止まっていた蒸気機関車とつながり、家族の会話を豊かにしてくれた。
そう考えると、キッチンに立つ時間さえ少し誇らしく感じます。
これからも、わが家の「ことば拾い」は続きます。
スーパーのレジ前、バスのアナウンス、YouTubeの決まり文句、そしてまた夕方の炊飯器。
どれもが小さな先生で、どれもが息子の辞書のページを増やしていく。
次はどんなフレーズが、どんな場面で飛び出すのか。
親として、ひそかに楽しみにしています。
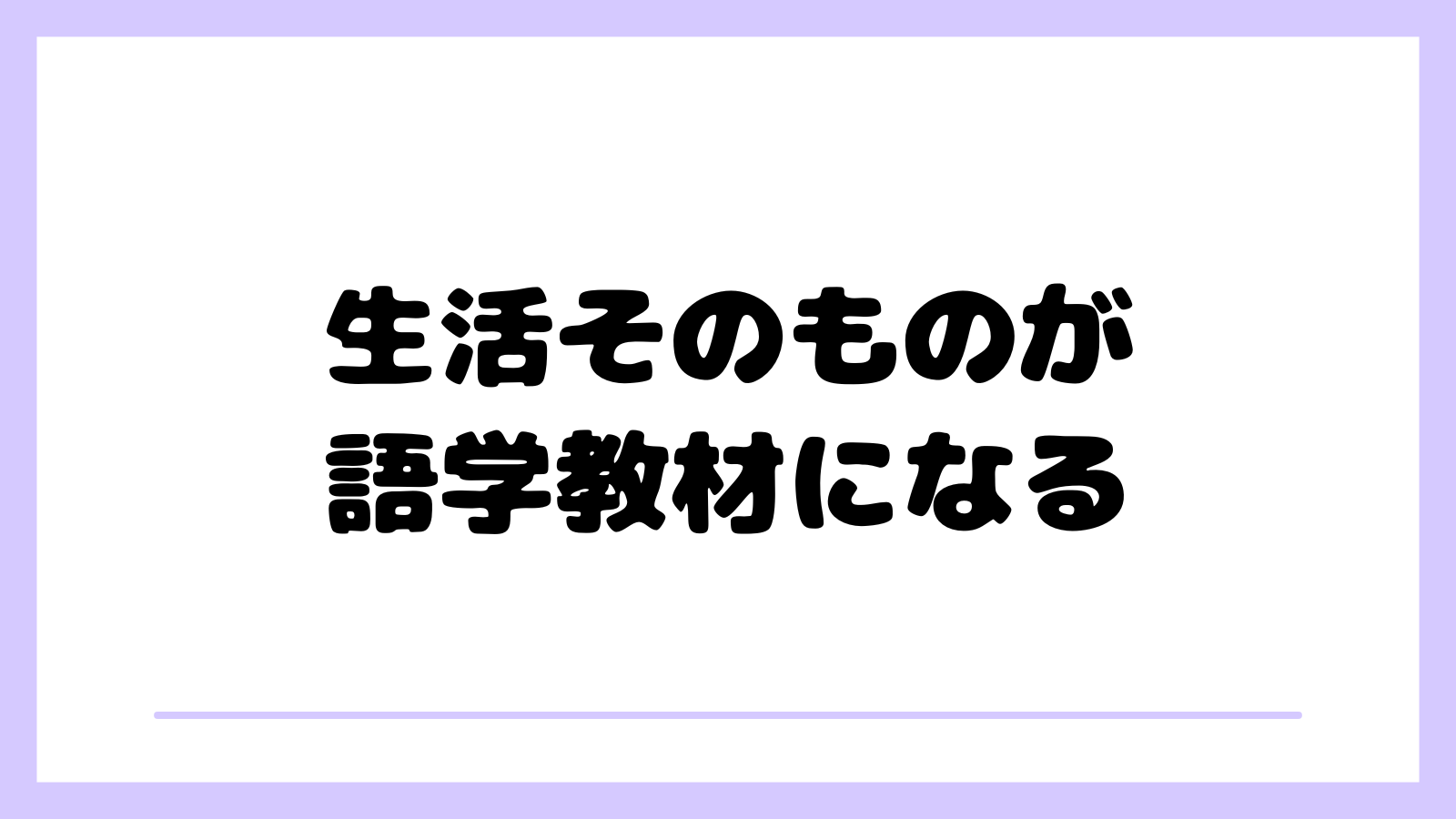
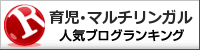
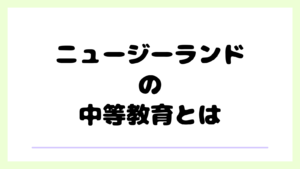
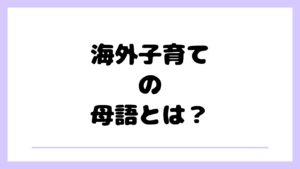
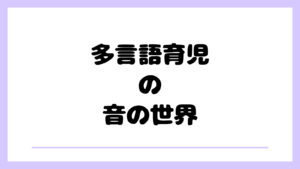
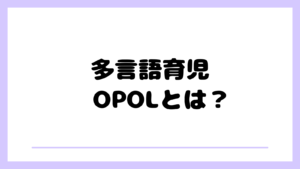
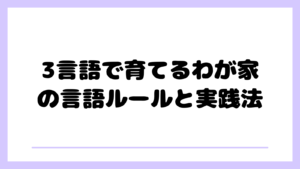
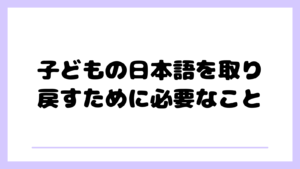
コメント